慢性頭痛を薬を使わずに改善に導きます。
頭痛とは、頭頚部に痛みが生じることです。頭痛は広く一般的な病気ですが、その種類はさまざまで、原因もそれぞれ異なります。鎮痛剤を服用すれば症状が治まるものもあれば、生命に関わる重篤(非常に重い)な病気の症状であることもあります。
一次性頭痛には片頭痛・緊張型頭痛・群発頭痛などが含まれ、もっとも多いのは緊張型頭痛です。また、二次性頭痛は多岐にわたる病気が原因となり、鼻や副鼻腔、口腔内の病変によるものもあります。
当院には偏頭痛、片頭痛、群発頭痛の患者さんがたくさん来院されます。
またこの様な慢性頭痛に良くあるパターンとして
頭痛が発生する。
↓
薬を飲む。
↓
頭痛が発生する。
↓
繰り返す。
この様なパターンを繰り返してしまい気づいた時には「頭痛薬が手放せない。」「一日の服用目安を超える量を服用してしまう。」の様な悪循環を繰り返してしまうことがあります。
薬を常用していると体はどうしても刺激に慣れてしまうので段々効かなくなってしまうのです。
また薬ですから当然副作用もあります。薬を常用していると体に取っては非常に負担がかかってしまいます。
当院では将来的なことも考え薬の量を減らしていく様にお伝えしています。
そして当院の鍼灸施術により頭痛の根本原因を解消することで慢性頭痛を改善に導きます。
慢性頭痛の主な分類。

⚪︎緊張型頭痛
緊張型頭痛は、頭痛もちの頭痛である“一次性頭痛”の中でもっともありふれたタイプの頭痛です。WHOと国際頭痛学会などとが共同で行った調査や、国内の疫学調査では、成人の有病率は約20%~40%と推計され、男女ともにみられますが、女性に多い傾向があります。
頭痛は、両側で感じることが多く、圧迫感やしめつけ感が主体で数十分から数日間持続することもあります。痛みの程度は軽度から中等度で日常的な動作で頭痛が悪化することはないため、家事や仕事は何とかかこなせます。このほか、頚部痛や肩こり、めまい感、浮遊感を伴ったり、光過敏や音過敏のいずれかを伴ったりすることがあります。片頭痛でみられるようなひどい吐気や嘔吐はありません。
頭痛の頻度によって、反復性緊張型頭痛(月1~14日)と、慢性緊張型頭痛(月15日以上)に大別されます。片頭痛との区別が難しい場合や、片頭痛と緊張型頭痛の両方を合併している場合があります。反復性緊張型頭痛は身体的あるいは精神的ストレスに対する反応として誰にでも起こりうる頭痛です。身体的ストレスには長時間の同一姿勢、不自然な姿勢、PCやスマートフォン使用、眼精疲労などが含まれます。また、本人はストレスと意識していない場合もあります。
慢性緊張型頭痛は、頭痛の頻度が多いため、生活の質(QOL)が大きく損なわれることがあります。
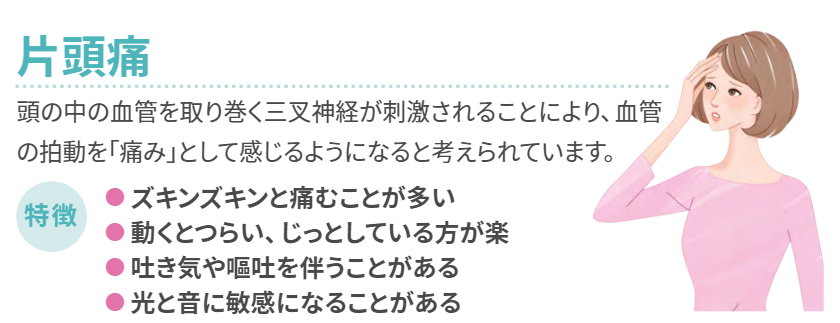
⚪︎片頭痛
片頭痛とは、吐き気や嘔吐、光や音に対して敏感になる症状をともなって、ズキン、ズキンと拍動するような強い痛みが頭の片側や両側に生じ、生活に支障をきたすことがある頭痛です。日本では1年間に約840万人が片頭痛に悩まされているというデータがあり、片頭痛に苦しむ患者さんは決して少なくありません。女性は男性の約4倍と多く、20歳代から40歳代の働き盛りに多く見られます。
片頭痛の病態は必ずしも全てが明らかになっていませんが、何らかのきっかけで、脳の血管が急激に拡張することで引き起こされると考えられています。たとえば、ストレスなどにより三叉神経が刺激され、神経末端より炎症物質を放出し、その炎症物質がさらに血管を拡張し、“ズキン、ズキン”と拍動する痛みをもたらす片頭痛を発症するといわれています。
また気候や気圧の変化、人混みなど環境の変化、寝すぎや寝不足といった生活リズムの変化や、飲酒、女性の場合は月経などの女性ホルモンの関与も推定されています。
⚪︎群発頭痛
群発頭痛とは、脳卒中など頭痛を引き起こす病気がないにもかかわらず慢性的な頭痛を繰り返す“一次性頭痛”の1つです。20~40歳代の男性に多く見られ、発症率は1,000人に1人程度とされています。まれな病気ですが、発症すると数週間~数か月にわたって、片方の目の周囲から前頭部や側頭部にかけて激烈な痛みが発作的に生じ、日常生活に大きな支障をもたらすのが特徴です。
群発頭痛の発症メカニズムは明確に解明されていない部分も多々あります。そのため、治療が難しく、一般的な“頭痛薬”とされる消炎鎮痛剤は効きません。また、一度発作を起こすと痛みを抑えるのが困難なケースも多いため、発症した場合は頭痛の発作を予防する治療が必須となります
群発頭痛の明確な発症メカニズムは分かっていないのが現状です。
しかし、群発頭痛は男性のほうが女性よりはるかに発症しやすいことから、男性ホルモンの過剰分泌が関与している説や、睡眠中など決まった時間に起こりやすいため体内時計の乱れが関与している説などが挙げられています。また、遺伝子の異常や何らかのウイルス感染などが発症に関与しているとの報告もあり、さまざまな要因が指摘されています。頭痛の発症機序として、脳神経の1つである三叉神経と自律神経の関与が想定されています。
これはあくまで一般的に言われている頭痛の概要と原因になります。
慢性頭痛の種類は様々ありますが慢性頭痛の本当の原因とは?の項目で記載している3つの要素が慢性頭痛の根本的な原因になっていると考えています。

一般的な頭痛の治療。
⚪︎非ステロイド性抗炎症薬
軽症~中等度の片頭痛の第1選択薬になります。市販薬でも「イブ®」が知られています。
他にも「ロキソニン®」や「カロナール®」などがあげられます。
これらは、「アラキドン酸カスケード」といって炎症が起こるメカニズムの一部を遮断することで痛みが起こらなくします。発症早期の服用が効果的とされています。
また「頭痛がひどいから」という理由で、これらの薬物を乱用すると「薬物乱用頭痛」といって薬物の内服が原因で頭痛になったり、胃や腎臓・肝臓を悪化させてしまう可能性があります。
⚪︎トリプタン製剤
トリプタン製剤は、片頭痛のメカニズムである血管の拡張を抑え、神経終末からの神経ペプチドの放出抑制・三叉神経核における痛みを伝える経路を抑えることで、片頭痛発作をおさえます。
薬物動態としては「片頭痛を抑える薬」に特化した薬といえます。偏頭痛のガイドラインでも「グレードA(強く推奨する)」に分類されています。トリプタン製剤には様々な形態があります。
⚪︎漢方薬
片頭痛の治療薬として漢方薬が使用されることもあります。最も有名なものは「呉茱萸湯(ごしゅゆとう)」ですが、非常に味が苦いので人を選びますs。他には「桂枝人参湯(けいしにんじんとう)」「葛根湯(かっこんとう)」「釣藤散(ちょうとうさん)」などがあげられます。
他にも、吐き気に対して吐き気止めを併用したり、吐き気止めを注射することで頭痛発作が軽減するという報告があります。
⚪︎食べ物に気をつける
チーズなどの発酵食品やチョコレート・赤ワインなどのアルコールを避けるようにしましょう。片頭痛もちの患者さんは、そうでない方に比べて高脂肪の食事やコーヒー・お茶の消費量が多いことも指摘されています。食品が誘因因子になるケースが26.9%認められるということで、一度食事内容も確認してみてください。
⚪︎大きな音や光など、誘発因子を避ける
痛くなったら、なるべく頭に余計な刺激を与えないことが大切です。早めに暗い静かな部屋で横になりましょう。色々な刺激があるほど片頭痛発作は起こりやすくなります。
他に誘発因子になりやすいのは「香水やにおい」「暑さ」「煙」など。心あたりのある方は頭痛が起こっている時間帯は避けるようにしましょう。
⚪︎頭痛が起こったら冷やす
例えば頭痛が起こったら痛いところを冷やしましょう。拡張した血管が収縮して楽になります。ただし、頸の血流が悪い方など、人によっては温めるほうがよい場合もあります。早めに対処することが大切です。
⚪︎睡眠はしっかりとり、ストレスをためない
1207人を対象とした片頭痛の調査によると片頭痛の誘因因子としてストレス(79.7%)、睡眠障害(49.8%)、夜更かし(32.0%)と睡眠やストレスを上げる方が多く見られています。
実際、睡眠不足や慢性的なストレスは片頭痛発作の頻度が高くなります。「ストレスをゼロにする」というわけにはいきませんが、睡眠をしっかりとってストレスをためないようにすると良いです。
⚪︎カフェインを上手に使う
カフェインが入った飲み物は一時的に頭痛が和らぐことがあります。しかし、乱用すると睡眠不足につながったりカフェイン依存症に陥ったりカフェイン自体が誘因因子になるケースがあるので飲みすぎには注意が必要です。「どうしても頭痛が止まらない」時に使うとよいでしょう。(他の薬の飲み合わせにも注意してください)

慢性頭痛の本当の原因とは?
⚪︎脳脊髄液の循環不良
特に注目しているのが、頭蓋骨周囲の筋肉や皮膚、筋膜の「緊張」と「滑走不全(動きの悪さ)」です。こうした緊張状態が続くと、頭蓋内を流れる脳脊髄液(CSF:Cerebrospinal Fluid)の循環が滞り、自律神経の中枢である視床下部や延髄といった領域の働きに影響を与えると考えられています。
脳脊髄液は、脳と脊髄を保護し、栄養供給や老廃物の排出、そして神経の正常な活動を支える重要な液体です。その流れがスムーズであれば、自律神経のバランスは保たれやすくなりますが、逆に流れが滞ることで神経系全体が「うまく切り替えられない」状態に陥りやすくなるのです。
当院に来院される慢性頭痛の患者さんのほとんどが頭がガチガチに固まっています。頭のコリが脳脊髄液の循環不良を起こすことで頭痛の大きな原因になっていると考えます。
⚪︎首周りでの神経圧迫
首周りで神経の圧迫があると頭に向かう血流が悪くなってしまいます。頭痛を感じる方は首や肩に慢性的なコリを感じている方が経験上多いです。
慢性的な首や肩のコリはマッサージやストレッチなどでは緩みづらい、首に関してはマッサージなどでは絶対に緩まないと言っても過言ではありません。慢性の肩コリや首コリでマッサージに行っても一時的には良いがすぐにぶり返してしまうのは、根本が緩んでいないからなのです。
慢性頭痛の解消には首周りを根本的に緩めることが大切になります。
⚪︎横隔膜の硬さ
横隔膜が硬くなると呼吸が浅くなります。呼吸は自律神経を整えるために非常に重要です。呼吸で取り入れられる酸素が少ないと慢性頭痛以外にも以下の様な支障が出ます。
・自律神経のバランスが崩れる
・代謝が落ちて疲れやすくなる
・身体のこわばり・肩こり・首こりにつながる
・脳で酸欠が起きて集中力が低下する
・病気につながる可能性もある
呼吸が浅い状態では、身体に緊張をもたらす交感神経が優位になり、反対に身体を休ませる働きを持つ副交感神経が抑制されてしまいます。
このように自律神経のバランスが崩れると慢性頭痛をはじめとした睡眠障害や食欲不振、胃腸障害、血流の悪化、めまい、息切れ、動悸などの症状を併発するリスクもあります。
慢性頭痛の解消には横隔膜の柔軟性を取り戻し呼吸をしやすくすることが大切です。
当院では鍼灸とクラニオセイクラルという整体法を組み合わせることで根本的に頭痛を解消させていきます。
最後に頭痛にお悩みの方へメッセージ。

当院では臨床の経験上、多くの「慢性頭痛は治る。」と考えています。
鍼灸で人間が本来持つ自然治癒力を上げていくと薬を併用せずとも必ず慢性頭痛は治ってきます。
薬は対症療法であり一時的なその場しのぎでしかないと言えます。
体の負担などを長期的な視点で考えると根本的に頭痛の原因を解消した方が多くのメリットがあると言えます。
当院では鍼灸とクラニオセイクラルという手法を使い慢性頭痛を根本改善へ導きます。
慢性頭痛にお悩みの方は当院にお任せ下さい。
ナイスボディー鍼灸治療院
代表 坂光佑太
03ー4530ー4198
〒143−0011
公式LINE→https://lin.ee/fr6nwp9
東京都大田区大森本町2丁目4−9パトリ大森1F
平和島駅東口徒歩3分 大森町駅徒歩8分 大森海岸駅徒歩15分 蒲田バス8分

